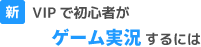いったい、どのキャプチャーボードを買えばよいのでしょうか。また、各製品はどこが違うのでしょうか。

キャプチャーボードを賢く選ぶためのコツを見ていきましょう。ポイントは、たった5個です。
PCに取り付ける方法を確認しよう
キャプチャーボードには外付型と内蔵型の2種類があります。これは、PCにどのようにして取り付けるのかという違いです。
| ノートPC | デスクトップPC | 液晶一体型PC | |
| 外付型 | ○ | ○ | ○ |
| 内蔵型 | × | ○ | × |
外付型
外付型は、USBでPCと接続するタイプです。ノートPCなら、このUSB接続タイプを購入しましょう。もちろんデスクトップPCでも使えます。
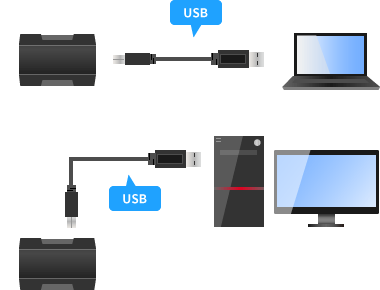
USBには、3.0(3.2)と2.0があります。USB 3.0で接続するキャプチャーボードの場合、PCのUSB 2.0端子に接続しても動作しません。

例外はありますが、USB 3.0端子は青色であることが多いはずです。PCに搭載されているUSB端子をあらかじめチェックしておきましょう。
USB 3.0は、厳密にはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)、またはUSB 3.2 Gen2(10Gbps)のことをさします。ただ、今回は細かいことは抜きにしました。
内蔵型
内蔵型は、PC内部のPCI Expressスロットにキャプチャーボードを取り付けるタイプです。
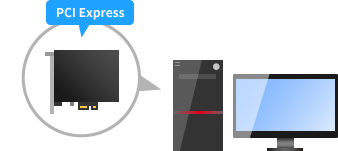
注意したいのですが、ノートPCには取り付けられません。PCI Express接続は、デスクトップPC専用の取り付け方法だからです。PCケースを開ける必要があるのです。
購入まえに、PCI Expressスロットに空きがあるか確認しておきましょう。PCI Express x1接続のキャプチャーボードの場合、x1スロットのほか、x4/x16スロットにも接続できます。
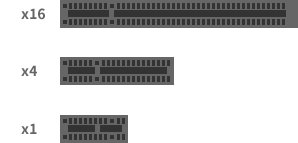
内蔵型キャプチャーボードをPCに取り付けると、PC背面は下図のようになります。このへんはイメージしづらいかもしれません。
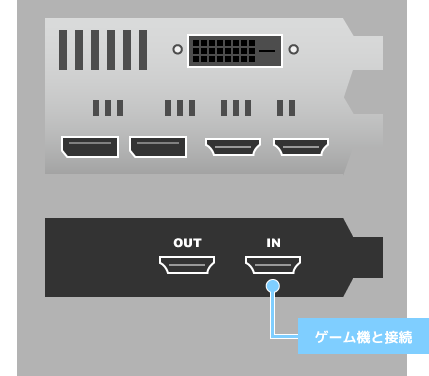
対応するゲーム機を確認しよう
接続できるゲーム機が異なる
キャプチャーボードによって、接続できるゲーム機が異なることがあります。
たとえば、近年のキャプチャーボードはHDMI端子を搭載しており、Switch2/SwitchやPS5/PS4を接続できるようになっています。

しかし、HDMI端子を搭載したキャプチャーボードとPS2は接続できません。なぜなら、PS2はHDMI接続できない仕様だからです。
そこで、どのようなゲーム機を接続したいのか考えたうえで、購入すべきキャプチャーボードを選びましょう。
最新のゲーム機の場合
近年のゲーム機は、HDMI端子を搭載しています。したがって、HDMI端子を搭載したキャプチャーボードを購入すれば接続できます。
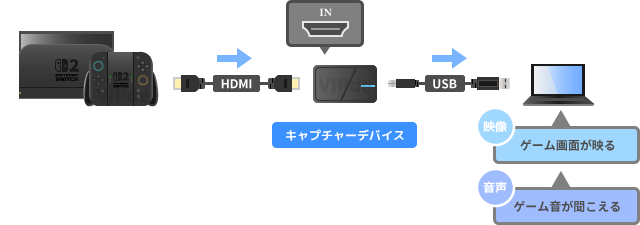
以下は、HDMI端子を搭載しているゲーム機の例です。
- Switch2、Switch、Wii U
- PS5、PS4
- Xbox One X、Xbox One、Xbox 360
- iPhone、iPad、iPod touch
レトロゲーム機の場合
レトロゲーム機の場合は、コンポジット端子(黄色い端子)を搭載したキャプチャーボードを購入します。たとえば、GV-USB2です。

HDMIキャプチャーボードは購入しないようにしてください。なぜなら、古い世代のゲーム機はHDMI端子を搭載していないため、同端子では接続できないからです。
以下は、レトロゲーム機の例です。
- Wii、GC、N64、SFC、NEW FC
- PS2、PS1
PS3の場合
PS3とキャプチャーボードをHDMI接続する場合は、HDCPというコピーガードに注意しましょう。そのままつなげても、基本的にゲーム画面はPCに映りません。別途、対策が必要になります。
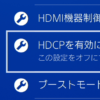
パススルー出力の有無を確認しよう
遅延とは
キャプチャーボードを使用し、PCに映っているゲーム画面を見ながらプレイすると、遅延(タイムラグ)を感じることがあります。
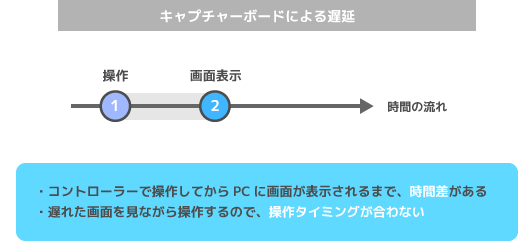
具体的には、
- 操作タイミングが合わない
- 操作が重い、遅い、鈍い
というときは、キャプチャーボードの遅延の影響を受けている可能性があります。重要なことですが、遅延のないキャプチャーボードは存在しません。
パススルー出力で遅延対策ができる
遅延を回避する簡単な対処法があります。それがキャプチャーボードのパススルー出力機能を使う方法です。
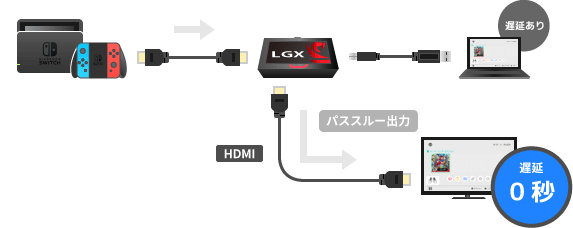
上図のように、キャプチャーボードとTV(モニター)をHDMIケーブルで接続します。TVのゲーム画面は、パススルー出力のおかげでキャプチャーボードによる遅延の影響を受けません。
分配器を使って遅延を回避する方法もありますが、パススルー出力があったほうが便利でしょう。



HDR・VRRは無視でもOK
このパススルー出力絡みで、「HDR対応」「VRR対応」と書かれたキャプチャーボードを見かけることがあるかもしれません。
しかし、もし用語の意味がわからなくても心配ありません。ほとんどのユーザーにとっては、大きなメリットではないからです。

エンコード方式を確認しよう
ソフトウェアエンコードと、ハードウェアエンコード
キャプチャーボードは2種類に分類できます。
- ソフトウェアエンコード
- ハードウェアエンコード
両者の違いは下表のとおりです。
| PCにかかる負荷 | 遅延の程度 | |
| ソフトウェアエンコード | 大きい | 小さい |
| ハードウェアエンコード | 小さい | 大きい |
この表の見方ですが、たとえばPCのスペックに自信がない場合は、ハードウェアエンコードのキャプチャーボードを買いましょう。
また、PCの画面を見ながらゲームをプレイしたい場合は、ソフトウェアエンコードのキャプチャーボードを購入します。
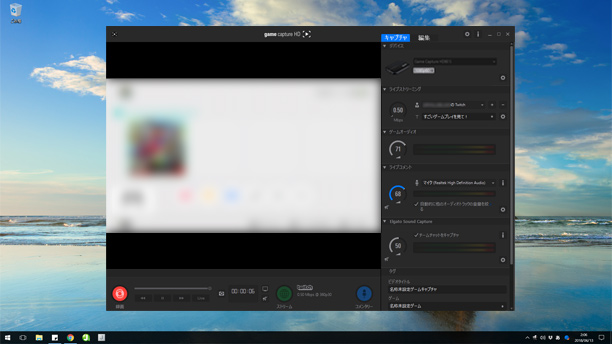
形式的な区別は、意味がなくなりつつある
ただ、エンコード方式はそこまで気にする必要はありません。というのも、近年は両者を区別する意味が薄れてきているからです。
たとえば、ハードウェアエンコードは遅延が大きいと書きました。しかし、なかには遅延軽減機能を搭載している製品もあります。その場合は、ソフトウェアエンコードの製品と同程度の遅延ですみます。

また、ソフトウェアエンコードの製品であっても、PCのGPUという部分を使って低負荷で録画できるものもあります。そうなると、ハードウェアエンコードの製品よりも負荷が小さいことがあるのです。

▲ソフトウェアエンコードの製品でありながら、低負荷で録画できるGC550。グラフィックボード、またはCPU内蔵のGPUを活用できます。
対応解像度を確認しよう
1080p/60fps対応の製品が主流
多くの人が1080p/60fps以下で録画・ライブ配信しています。
したがって、キャプチャーボードのほうも録画解像度が1080p/60fps対応の製品を選べば問題ありません。
4K解像度に対応した製品も登場
2016年以降、解像度が4Kに対応しているゲーム機も発売されるようになりました。
- Switch2
- PS5 Pro
- PS5
- PS4 Pro

となると、4K解像度対応のキャプチャーボードを意識する人もいるかもしれません。しかし、4K対応製品の必要性はそこまで高くありません。
ただ、長い目で見て購入しておくのは悪くない選択肢です。値が張るので、購入するまえに製品情報を吟味しましょう。
どれを買うべきか、おすすめは
ここで紹介する製品は、いずれも以下の点で共通しています。
- 外付型
- パススルー出力機能あり
- 1080p/60fps対応
定番メーカーの製品が欲しい人へ
まずは、GC551G2を押さえておきましょう。AVerMediaという、キャプチャーボードでは定番メーカーの製品です。
付属のキャプチャーソフトには、実況動画を作れる録画機能はもちろんのこと、ゲーム配信機能が搭載されており、2ステップの設定をするだけでYouTubeやTwitchでライブ配信できます。「ゲーム配信は難しそう」と考えている人ほど、拍子抜けするかもしれません。それくらい簡単です。
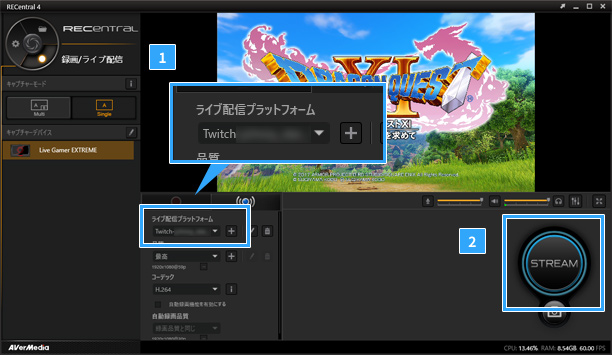
PCの負荷については、一般的な性能を有しているPCなら心配ないでしょう。GPU(グラフィックス機能のこと)を使うこともできるからです。
遅延も気にするほどではありません。ただ、遅延の感じ方はゲームジャンルによって大きく違ってきます。必要に応じてパススルー出力を使いましょう。
GC551G2については、下記ページをご覧ください。

コスパのよい製品が欲しい人へ
コスパ重視で考えるならGV-USB3HDS/Eもよいでしょう。実売価格は2万円を切ります。
この製品は、動画編集ソフトであるPowerDirector 18が付属されています。もし編集ソフトを使ってみたいということであれば、まちがいなくお得です。機能は制限されていますが、筆者は実況動画を編集するうえで不便さを感じませんでした。
ただ、付属ソフトはあまり使いやすくはありません。もし別のソフトを使いたい場合は、OBS Studioがおすすめです。


それでも悩むなら
もう少し検討したいのであれば、以下のページもご覧ください。最新情報を掲載しています。
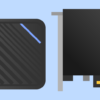
2006年から15年以上、ゲーム実況のやり方の解説記事を書いています。書いた記事数は1,000本以上。ゲーム配信、ゲーム録画、動画編集の記事が得意です。
記事はていねいに、わかりやすく!ゲーム実況界の教科書をめざしています。